〜栄養と声かけ、我が子の変化を通して感じたこと〜
こんにちは、食育栄養コンサルタントのたまごごはんです。
今日は、息子サンボの「行き渋り」と向き合ってきた4年間の中で、私がやっと気づいた“ある大切なこと”についてお話します。
年長から始まった「行き渋り」——その裏にある“がんばりすぎ”
わが家の息子サンボは、保育園の年長の頃から登園渋りが始まりました。
当時の私は「どうすれば前向きに行けるようになるんだろう」と毎日、声かけを模索していました。
「大丈夫だよ」
「先生が待ってるよ」
「楽しいことがあるよ」
「今日はおいしいお給食だよ」
励ましや共感、寄り添い、時には少し厳しい言葉も——。どれも、すぐには効果がなく、涙とパニックの朝が続いていました。

「声かけ」が子どもの心に届かない理由
当時の私は、息子が“怖くて行けない”とか、“嫌なことがある”とか、目に見える「行きたくない理由」があると思っていたんです。でも違いました。
あとになってわかったのは——
サンボは“頑張りすぎていた”んです。
たくさんの刺激、人間関係、期待されること。
「ちゃんとしなきゃ」「失敗できない」「迷惑をかけたくない」
そんな思いを小さな体に抱えて、毎朝、心と体がギュッと緊張していたのです。
私自身も「がんばりすぎていた」ことに気づかされた日
ある日、職場の同僚がこう言ってくれました。
「たまごごはんさんって、いつもがんばりすぎてませんか?」
「肩の力、抜いていいですよ。もっと適当でも大丈夫ですって」
その言葉に、私はハッとしました。
そういえば私も、家でも仕事でも常にアクセル全開。手を抜くことは“悪”だと思っていたし、やりきらないと気が済まなかった。
でも、その同僚が毎回やさしく「ゆるくいきましょう」と声をかけてくれて、ふと気持ちが軽くなる瞬間があったんです。
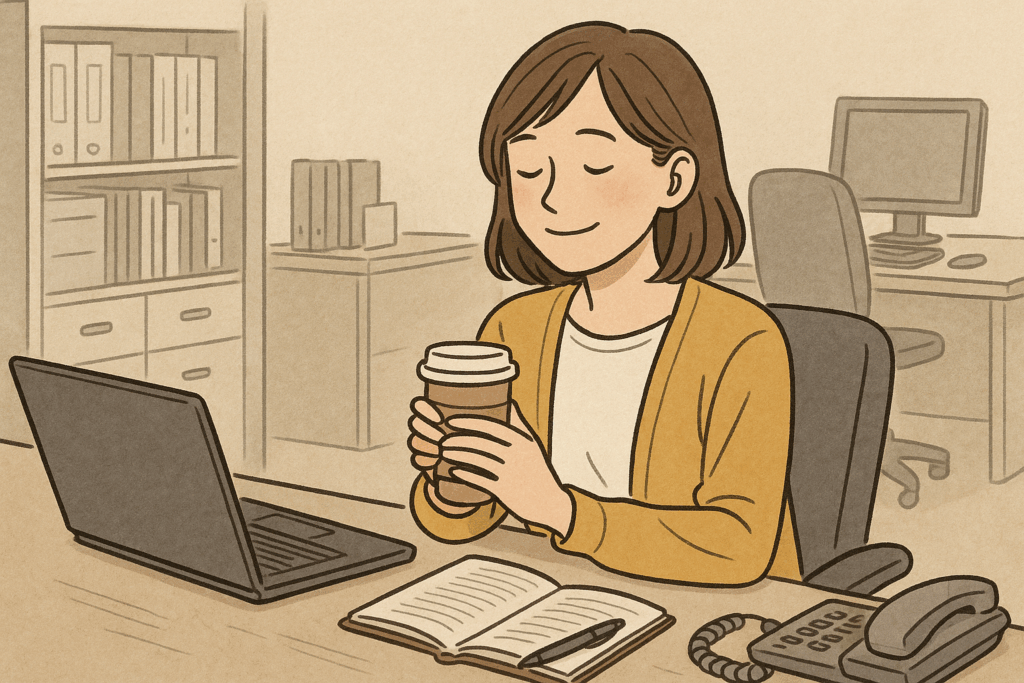
「がんばらない声かけ」が息子の心をほどいた
そこから、私の声かけは大きく変わりました。
月曜日の朝、息子が「今日はついてきて」と言うとき——
その緊張した肩にそっと手を置いて、私はこう声をかけるようにしたんです。
「また頑張りすぎてるよ。肩にすごく力が入ってるね。」
「月曜日はしんどくて当たり前なんよ。」
「みんなそう。パパもママも先生も、クラスのみんなもしんどい。」
「だから今日はゆる〜く行こ。がんばらなくていいんよ。」
「もうすでにサンボはがんばってるから、それ以上は何もいらない。」
この声かけに変えてから、サンボは少しずつ笑顔で登校できるようになりました。
「今日は、ちょっと行けそうな気がする」
「なんか、大丈夫かも」
そんな言葉が出てくるようになったのです。
「頑張る力」だけじゃなく「抜く力」も教えよう
学校に行けなくなるお子さんの多くは、決して「怠けている」わけではありません。
むしろ逆で、“がんばりすぎて動けなくなっている”子が本当に多いのではないでしょうか。
私たち親も「今日こそは行けるかな」「なんで行けないの」と肩に力が入っていきます。
でも、それが子どもにも伝わり、お互いにギュッと固まってしまう。
本当に必要なのは、「力の入れ方」より「抜き方」かもしれません。
人生はずっと続くマラソン。全力疾走ばかりでは倒れてしまう。
だから、意識して抜くこと、ゆるめること——それもまた、生きる技術のひとつなのです。
栄養の面から見た「心のゆるめ方」——ナイアシンとマグネシウム
実はこうした心と体の“緊張”には、栄養の影響もとても大きいんです。
特に関係が深いのは、以下の2つの栄養素。
◆ナイアシン(ビタミンB3)
不安やイライラの軽減に関係する 脳内で「セロトニン」の材料になる ストレス耐性の向上に

◆マグネシウム
神経の興奮をしずめる役割 睡眠の質を高める 筋肉の緊張をゆるめる

息子サンボも、栄養療法を取り入れる中で、ナイアシンやマグネシウムを補うことで明らかに落ち着きが出てきました。
「食べること」「整えること」も、声かけと同じくらい大切なんです。
▼サンボが飲んでいるサプリはこちらの記事で詳しく紹介しています。
最後に:がんばらなくても、ちゃんと育ってる
私たち親はついつい、「ちゃんと行けたか」「みんなと同じか」に目を向けてしまいます。
でも、ゆっくりでも、寄り道しても、ちゃんと子どもは育っています。
頑張らせるより、寄り添う。
前に進ませるより、今を安心させる。
そのほうが、ずっと近道だったりするんです。
※この記事にはアフィリエイトを含みます。
たまごごはん
食育栄養コンサルタント/デジタル業界20年
小学2年生の息子を育てる母。自身も小学1年生で登校拒否を経験し、息子も年長から登園拒否に。試行錯誤の末、「栄養が心と体に与える影響」に着目し、改善を実感。2025年に食育栄養コンサルタント資格を取得し、成長期の子どもに必要な栄養を学ぶ。
現在は、登校拒否に悩む親御さんへ向けて、栄養と食育の視点から解決策を発信中。




コメント